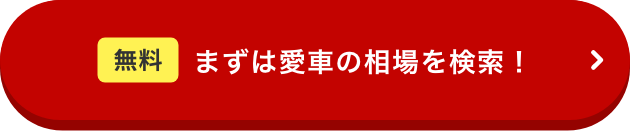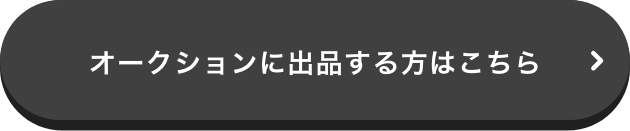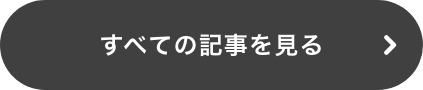目次
[
− 閉じる
]
バイクを所有している方は、廃車手続きをしない限り、自治体に税金を納めるのが義務です。そのため売却や譲渡をしても、条件によって手続きをしなければ納税義務はなくなりません。
そこで必要となる処理が軽自動車税の停止手続き、通称「税止め」です。この記事では、税止めの概要や必要書類、手続き方法についてご紹介します。
グーバイク買取では、愛車の売却を検討している方のご相談を受け付けております。 買取店3,000店が参加するオークション形式により、愛車の魅力を理解し、高値で買い取ってくれる店との取り引きが可能です。
まずは、無料の愛車相場検索をご利用ください。
税止めとは?バイクにかかる税金の種類と税止めについて
ここでは、そもそも「税止め」とは何か、バイクにかかる税金の種類について詳しく解説します。
税止めとは
バイクを所有している人には、軽自動車税が課せられています。税額は排気量によって異なり、車両登録内容の申告に基づいて決められています。
売却などでバイクの所有者がほかの都道府県に移った場合は、元の所在地で税申告処理をする必要があります。運輸支局や軽自動車検査協会への届出が完了していても、課税処理を行なう自治体とは連携していないため、別途手続きが必要です。
この、課税を止めるために管轄の自治体へ届け出ることを、「税止め」といいます。
バイクにかかる税金の種類
バイクにかかる税金は、年1回の軽自動車税と、車検時に支払う自動車重量税があります。このうち、税止めの手続きが必要なのは軽自動車税です。
軽自動車税は、4月1日時点の登録内容に基づいて5月頃に納付書が発行・郵送されるため、3月末までに手続きを完了しなくてはなりません。
なお、排気量ごとの軽自動車税は次のとおりです。
- 50cc以下:2,000円
- 50cc超~90cc以下:2,000円
- 90cc超~125cc以下:2,400円
- 125cc超~250cc以下:3,600円
- 250cc超:6,000円
税止め手続きが必要になるケースは?
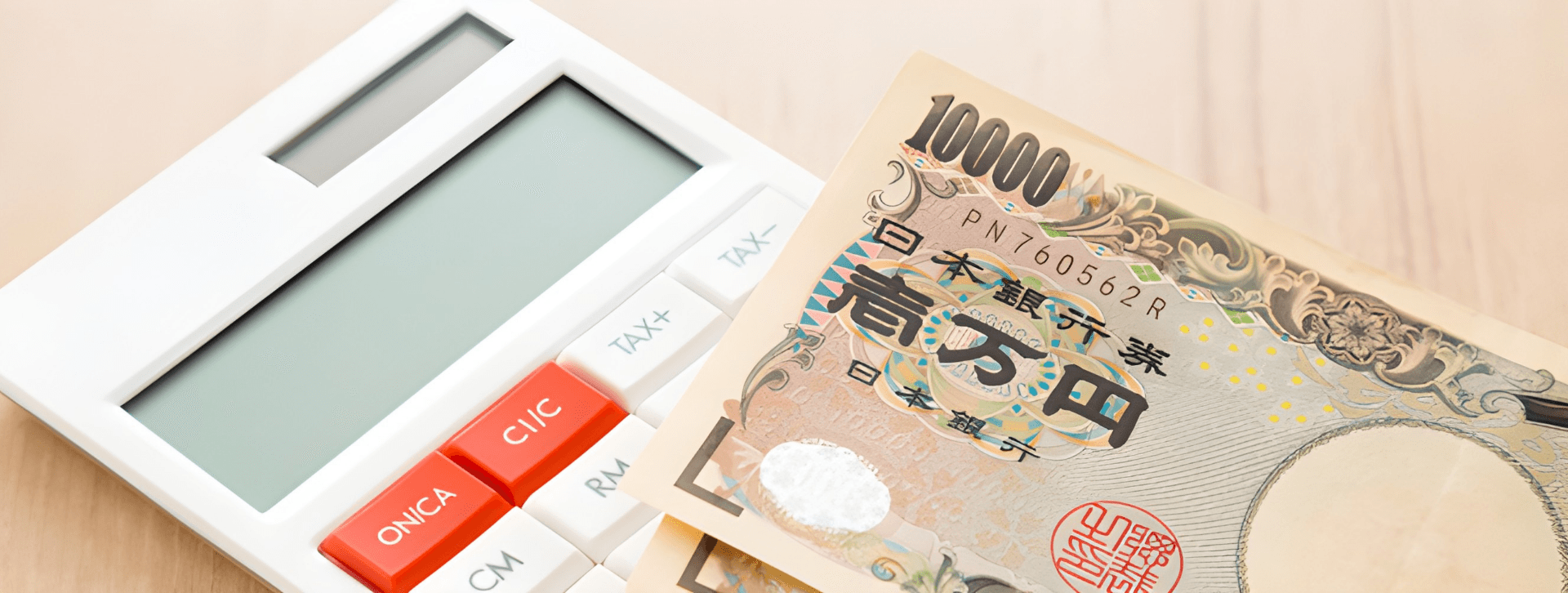
税止めの手続きは、必ずしも必要なわけではありません。ここでは、税止め手続きが必要なケースと不要なケースをそれぞれ確認していきましょう。
税止め手続きが必要になるケース
税止め手続きが必要となるのは、排気量が125ccを超えるバイクです。125cc以下のバイクは登録が自治体のため、名義変更や廃車処理を行なう際に一緒に処理され課税もストップします。
125ccを超えるバイクのうち、県外へ引越した場合や、県外の方へバイクを売却または譲渡して名義変更した場合に税止め手続きが必要です。手続きは旧所在地の自治体で行ないます。
自治体が異なっても、同じ都道府県内であれば情報が共有されるため、手続きは不要です。
税止め手続きが不要なケース
先ほど述べたとおり、125cc以下のバイクは税止め手続きが不要です。また125cc超のバイクについても、登録している都道府県内での廃車や住所変更、所有者変更であれば手続きは必要ありません。
さらに、軽自動車検査協会や運輸支局に、自治体への申請代行を依頼した場合、自身での税止め手続きは不要です。管轄の運輸支局によっては申請代行に費用がかかるものの、手続きの手間を減らせることや、手続きの失念による課税を回避できるのがメリットです。
税止めに必要な手続き書類と手続きの流れ

税止め手続きの必要書類と手続きの流れは、次のとおりです。
税止め手続きの必要書類
税止めの手続きは、以下の書類のうちいずれか1つがあれば実施できます。
ただし、自治体によっては書類を限定している場合もあるため、まずは手続きをする自治体に確認しましょう。
新ナンバーの自動車検査証の写しや、変更後の軽自動車届出済証の写しを取得するには、新しいオーナーに依頼しなければなりません。
スムーズに手続きできるよう、軽自動車税申告書はしっかりと保管しておくのが懸命です。
税止め手続きの流れ
税止めの手続きは、先ほど挙げた必要書類を窓口にて提示、または郵送して申告します。FAXでの受け付けが可能な場合もあるため、事前にお住まいの自治体に手続き方法の確認をしておくとよいでしょう。
手続きについて申告者へ連絡を取ることも想定されるため、余白に連絡先の記入を求めている自治体も多いようです。
また、自治体によって手数料がかかる場合もあるため、この点も事前に確認するとよいでしょう。なお、手続きは元の所在地の自治体で行なう点にご注意ください。
軽自動車税が課税された場合の対処方法
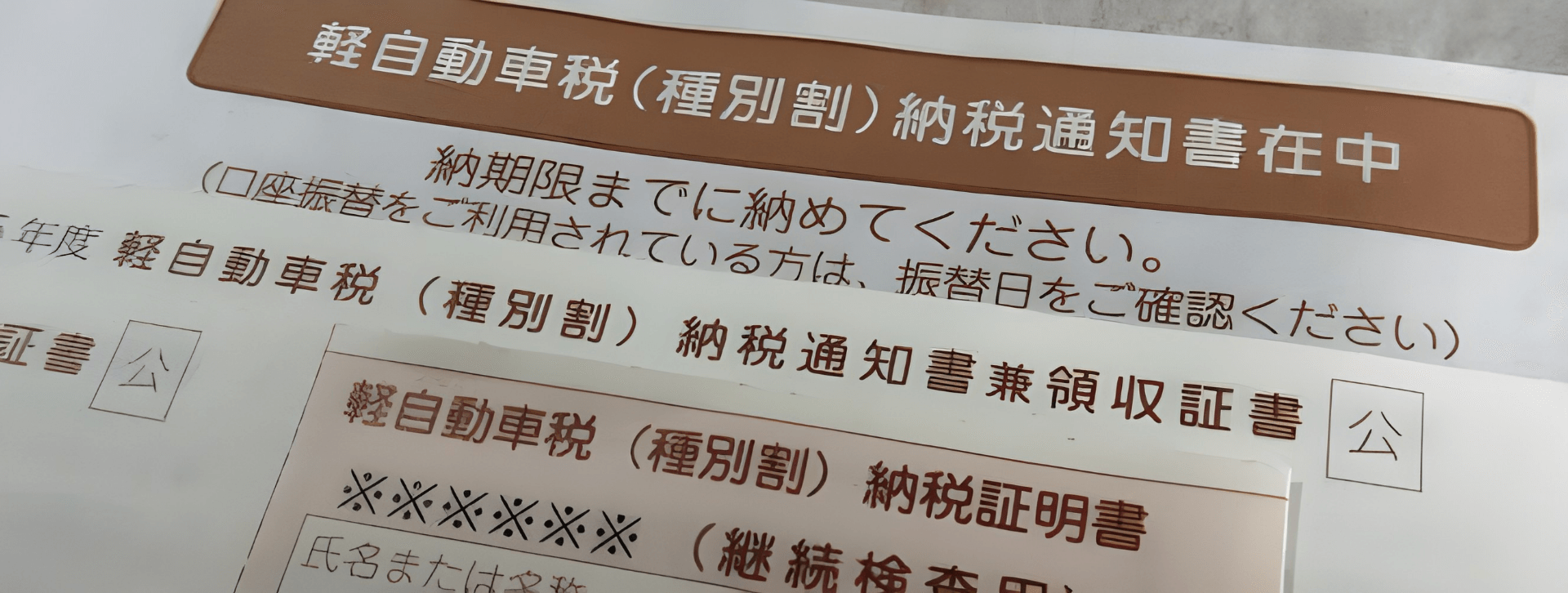
バイクを売却したのに税金の支払い通知が来た場合は、税止め手続きが完了していない可能性があります。まずは以下の行動を取りましょう。
バイクの税金を管理している部署は、「税務課」や「課税課」など自治体によってさまざまです。わからない場合は、総合窓口にて、バイクを売却したのに税金の請求がきた旨を話せば、管轄している部署に連絡が取れます。
役所の説明をよく聞き、早めに税止めの手続きを行ないましょう。
バイクの税止め手続きの注意点
納税でのトラブルを避けるため、バイクの税止め手続きに関する注意点を確認しておきましょう。
軽自動車税は払い戻しされない
自動車税と違って、軽自動車税には月割制度がありません。軽自動車税は年に1回支払いますが、年度の途中で廃車手続きや名義変更手続きをしても支払い済みの税金は払い戻しされないので注意しましょう。
また、すでにバイクが手もとにないなどの場合でも、4月1日までに手続きが完了していないと軽自動車税の納税義務が発生します。
車検切れの場合も免税されない
手もとにあるバイクが車検切れの場合も、廃車手続きをしなければ課税されてしまいます。
先述したとおり、毎年4月1日時点の登録内容をもとに課税されるため、廃車手続きは3月31日までに終わらせましょう。廃車手続きが4月2日以降になってしまった場合は、納税しなくてはなりませんので注意が必要です。
滞納すると延滞金が発生する場合がある
軽自動車税を期限までに納付しないと、送付された納付用紙は使用できなくなります。納税するには、自治体の担当者へ連絡が必要です。
また、期限を過ぎての納付は延滞金が発生する場合があります。督促や警告などを無視し続けると資産を差し押さえられる可能性もあるため、速やかに納付することが大切です。
まとめ
税止めとは、バイクの売却などで名義変更したり、引越したりした際に、軽自動車税の課税を停止するために必要な手続きです。ただし、税止めが必要となるのは125ccを超えるバイクで、所有者の所在がほかの都道府県に変更になった場合です。
適切に申請をしないといつまでも軽自動車税の納付書が届くことになるため、必要書類や手続きの流れを確認し、忘れずに申請しましょう。
グーバイク買取では、愛車の無料相場検索を実施しています。匿名、無料で、お手持ちのスマートフォンからお気軽に相場検索が可能です。
また、出品も匿名ででき、愛車の情報や画像を登録すればOK。買取店が付けた金額を確認してから売却するかを決めることができます。まずは一度、ホームページをご覧ください。
本記事は、2024年8月26日の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。